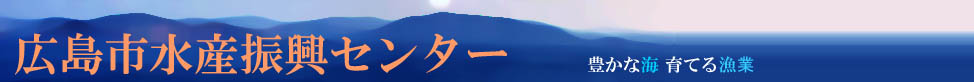平成16年度海辺の教室開催の様子
平成16年4月 プランクトン
今年度の最初の海辺の教室は、「プランクトン」でした。
プランクトンの種類・役割、また、顕微鏡の使い方やなぜ赤潮が発生するかなどについて説明しました。
顕微鏡で、生きたプランクトン、水産振興センターで魚やカニの赤ちゃんを育てる時に与えている動物プランクトン(シオミズツボワムシ)や広島湾の定期調査で採取(さいしゅ)した各月のプランクトンを観察しました。
また、プランクトンは小さいイメージがあると思いますが、肉眼でも見えるプランクトンのクラゲを観察しました。
皆さん、顕微鏡で観察したプランクトンをうまくスケッチしていました。
 |
 |
| うまく顕微鏡が使えたかな |
顕微鏡で見えた動物プランクトンをスケッチしています |
平成16年5月 メダカの育て方
メダカを育てる時の重要なポイント(飼育水の作り方や交換の仕方、えさの種類や与え方など)やメダカの特徴(とくちょう)などについて説明しました。
また、生きたメダカの卵の顕微鏡観察では、メダカの心臓(しんぞう)や 血液が流れているのを興味をもって観察していました。
 |
 |
| メダカのフンの掃除(そうじ)の仕方を説明しています |
家でもメダカの観察をしよ〜と |
メダカの卵の発生段階
 |
|
|
時間が経つにつれ卵が変化していく様子がわかります
写真は左から3日後、4日後、7日後、10日後
|
平成16年6月 アユ−川のいきもの−
川の魚を代表するアユの生態、漁法、海水と淡水における魚の適応能力(てきおうのうりょく)、生息環境(せいそくかんきょう)のほか生物の大切さ等について学習しました。
実習では、他の魚とは違ったアユ特有のヒレや口の観察をしたり、また、解剖(かいぼう)により、ウキブクロなどがどこにあるのかなど魚の体のしくみをテキストを見ながら調べました。
皆さんが、ふだん何気なしに食べている魚でも、体の中にはいろいろな働きをしている器官(きかん)があること、そして、いき物や食べ物を大切にする心を学んでいただけたのではないかと思います。
 |
 |
| 鱗(うろこ)を顕微鏡で見てみようかな |
これは、アユの鱗(うろこ)です 木の年輪(ねんりん)のようなものが見えます |
平成16年7月 育てる漁業
沿岸漁業(えんがんぎょぎょう)は、魚のとりすぎや海の汚れなどで魚が減って、だんだんふるわなくなってきています。そのため、海をきれいにしたり、栽培漁業(さいばいぎょぎょう)などに力を入れたりして、沿岸の水産資源を増やすことが大切になっています。
今回、育てる漁業として、クロダイなどの種苗生産(しゅびょうせいさん)などについて説明し、当センターで育てたクロダイの赤ちゃんを放流しました。
 |
| うわー元気に泳いている |
種苗生産とは、親の魚から卵をとり、それをふ化させて一定の大きさまで育て、海や 川へ放流してやることをいいます。
平成16年8月 海辺のいきもの
夏休み中、子供たちは海へ行き、カニや魚などを何種類か採ったり、観察したようです。
今回、約40種類の海辺の生物を観察し、中には、見たこともない生物もいたのではないかと思います。
また、藻場、干潟、磯の状態を再現した水槽を見てもらい、藻場、干潟などの生物の観察や、また、これらの場所の大切さを学びました。
他に、アサリの砂もぐり、フジツボの餌のとり方などの観察をしました。
 |
 |
| ウニやヒトデなどの歩き方やアサリの砂もぐりを観察しました |
フジツボはどのように餌(えさ)をとっているのかな |
平成16年9月 魚の年齢
魚の体のしくみや魚の年齢を調べることができるウロコ、耳石(じせき)、脊椎骨(せきついこつ)などについて説明しました。
実習では、魚から耳石やウロコを取り出し、それらを顕微鏡で観察して魚の年齢を調べました。
耳石を見つけることに苦労していたようですが、発見したときには子供、保護者共に大変喜んでいました。
今日帰って、魚の煮つけをして耳石を見つけさせたいという保護者もいました。
 |
 |
|
親子ともにとても楽しそうでね
|
これはクロダイのウロコを拡大しています
さて何歳ぐらいでしょう
|
平成16年10月 かまぼこ
今回のテーマは「かまぼこ」で、人気あるテーマの一つです。
かまぼこの歴史などや、実際に魚の身をすりつぶしてかまぼこ作りをしました。親子共に楽しく学べたのではないかと思います。
かまぼこには、クロダイ、シログチ、メンタイの魚を使いました。
手づくりで、出来立てのかまぼこは、なかなか美味しかったようです。
 |
 |
| 魚の身を細かく切って、すり鉢で食塩を2%ぐらい入れて糸が引くくらいまで練(ね)ります。食塩を入れることでかまぼこの弾力(だんりょく)が出ます |
がんばって作ったかまぼこは美味しかったですか?何かかまぼこが輝いて見えるようですね |
かまぼこの作り方(板かまぼこ2個分)
材料
- メンタイの切り身:一匹分
- 食塩(精製塩):2〜2.5g
- かたくり粉:20g
- みりん:8ml
- 卵白:M玉一個分
- 砂糖:12g
手順
- メンタイの身を水にさらして血や脂を洗い流す 。
- ふきんなどで水気をよく取り除き、包丁などでみじん切りにして、すりばちですりつぶす 。
- 食塩を入れてねると粘りが出てくる。糸が引くくらいねる。
- その他の調味料をすり身の少しずつ混ぜる。
- かまぼこ板にスプーンなどで盛りつけて形を整える。
- ラップでくるんでゆっくりと「す」が立たないように約20分蒸す
ポイント
- 盛りつけるときに水を付けながらやるとなめらかに仕上がります。
- ネギ、ショウガ、みそなどを入れてもおいしい。
平成16年12月 かき養殖
今回は「かき養殖」で一番人気のテーマです。
採苗(さいびょう)や抑制(よくせい)などの養殖方法や、体の構造やエサの取り方などの生態(せいたい)の説明を熱心に聞いていました。
カキ打ち体験では、最初は悪戦苦闘(あくせんくとう)していましたが、すぐに要領(ようりょう)を得る子供が多く、上手に殻から身を取り出していました。
 |
 |
| 皆さんかんばっていますね |
うまく身を取り出していますね |

|
鮮度(せんど)の良いカキとは
●身がこんもり盛りあがり、つやがあって弾力(だんりょく)にとんでいる。
●黒い縁(ふち)の部分と身の乳白色(にゅうはくしょく)がくっきり際立っている。
●貝柱が身からはなれず半透明(はんとうめい)である。
|
平成17年1月 ノリ養殖
広島市のノリ養殖は、昔は盛んでした。現在では僅かしか養殖しておらず、参加した子供たちはノリ養殖風景をほとんど見たことがないようでした。
昔の道具を使い、ノリすき体験をしました。自分ですいたノリを持って帰り乾燥して食べたいという子供たちがほとんどでした。
また、乾燥したノリは普段目にすることがありますが、生ノリは見たり、食べたことはないようでした。
 |
 |
| 昔に使っていた簀(す)と簀枠(すわく)で 紙をすくようにノリをすきました |
このノリはどうですか |
平成17年2月 かき養殖
小学生から質問がありましたので、その内の1問を紹介します。
- 質問
- 販売しているカキには「生食用」、「加熱調理用」と表示していますが、どのような違いがあるのですか?
- 答え
- この表示の違いは、そのカキが採取された海域により分けられています。河川などの影響を受けやすい沿岸部で獲 れたカキを「加熱調理用」、また、沖合いで獲れたものを「生食用」と表示しています。「加熱調理用のカキ」は、「生食用のカキ」よりも鮮度は悪いとイメージされている方が多いようですが、生食用と加熱調理用の鮮度は同じです。
 |
 |
| 一番人気のテーマで、多数の参加がありました |
うまくできたようです |
平成17年3月 ワカメ養殖
今回は、ワカメの養殖の方法、海藻の種類や海藻の森が魚たちにとって大切な場所になっていることなどについて説明しました。
参加した小学生の皆さんは、ほとんどの方が海で海藻を見たことがなく、また、ワカメのもともとの色が褐色(かっしょく:こげ茶色)であることを知らなかったようです。
実習では、塩蔵ワカメを作りました。褐色の生のワカメを熱湯へ入れると一瞬にして緑色に変わるとびっくりしていました。また、ワカメの標本を展示し、その大きさにはびっくりしていたようです。
 |
 |
| ワカメを熱湯へ入れると一瞬にして緑色に変わりました |
これからゆでまーす |
 |
|
身長より大きいワカメ
|
 |
|
海藻は、色によって、緑藻類(りょくそうるい):写真左、褐藻類(かっそうるい):写真中、紅藻類(こうそうるい):写真右と大きく3つのグループに分けられます。
海に生えているワカメは、褐色(かっしょく:こげ茶色)をしており、褐藻類(かっそうるい)のグループに分けられます。
|