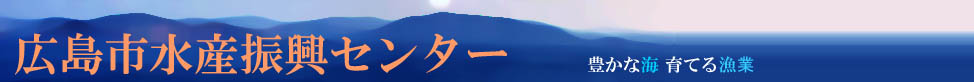つくり育てる漁業や水産振興センターで育てている魚介類の赤ちゃん(種苗)について学習した後、スズキの餌やりやマコガレイ稚魚の放流体験を行いました。水産振興センターで育てている種苗については、コチラをご覧ください。
平成23年度海辺の教室開催の様子
平成23年4月「育てる漁業:マコガレイ」

つくり育てる漁業について学習しました。栽培漁業と養殖漁業の違いは分かったかな。

実際にマコガレイを育てている水槽を見学しました。

卵を産んでもらうために育てている親スズキに餌やりをしました。大きなスズキが餌を食べる姿は大迫力です。

卵を抱いた親モクズガニを観察しながら、担当者から飼育の大変さを教えてもらいました。当日は、テレビ取材もありました。

「大きく育ってね。」と声をかけながら、マコガレイの稚魚を放流しました。
平成23年5月「海辺のいきもの」
潮の満ち引きや干潟の役割について学習し、水産振興センターのすぐ横にある干潟でいきもの採集を行いました。採れたいきものは、持ち帰ってどんな種類か調べました。

海辺のいきものにとって、干潟がとても重要であることを学習しました。

センターのすぐ横にある八幡川河口の干潟でいきものを採集しました。

採れたいきものをセンターへ持ち帰り、みんなで種類を調べました。

短時間でしたが、こんなにたくさんのいきものが見つかりました。

マメコブシガニ

オキシジミ

テッポウエビ

ハゼの仲間
平成23年6月「メダカの育て方」
メダカの生態やオスとメスの見分け方について学習し、実際に顕微鏡でメダカの卵を観察したり、メダカが流れに逆らって泳ぐ様子を観察しました。また、家庭でのメダカの育て方についても実際の水槽を見ながら学習しました。

メダカがすんでいる場所やオスとメスの見分け方を学習しました。

顕微鏡を使って卵を観察しました。ふ化直前だったので、心臓が動く様子が見えました。

メダカの卵には、ものに付着するための糸(付着糸)があります。

メダカを入れる数や卵を産ませるためのポイントについて、水槽を見ながら学習しました。ペットボトルを使った飼育方法も紹介しました。
平成23年7月「チリメンモンスター」
チリメンジャコの原料になるカタクチイワシの漁法やチリメンジャコができるまでの工程について学習した後、チリメンモンスターを探して種類を調べました。お気に入りのチリモンは、寒天で固めたりラミネートをして持ち帰りました。当日は、テレビの取材もありました。

ルーペを使ってチリモンを探します。珍しいチリモンを探すのに大人も夢中です。

見つけたチリモンの種類を調べます。エビやカニの幼生は親と違う形をしているので違ういきもののようです。

見つけたチリモンを画用紙に張り付ければ立派なコレクションになります。

市販の寒天を使ってお気に入りのチリモンを固めて持ち帰りました。チリモンが海に浮かんでいるようです。
今回見つかった「チリモン」の一部

左から順に、カワハギの仲間、アジの仲間、ヒイラギ、カサゴの仲間、タイの仲間

左から順に、タチウオ、タツノオトシゴ、イカの仲間、シャコのアリマ幼生、イセエビのフィロゾーマ幼生
平成23年8月「プランクトン」
水産振興センター近くの海で、みんなでプランクトンネットを使ってプランクトンを集めました。集めたプランクトンを顕微鏡で観察してみると、カキなどの餌になる植物プランクトンや魚などの餌になる動物プランクトンをたくさん見つけることができました。普段は目に見えない小さなプランクトンが、海の中でとても大切な役割を果たしていることが分かりました。

プランクトンの種類や食物連鎖におけるプランクトンの役割などについて学習しました。

海に出て、実際にプランクトンを集めました。どんなプランクトンが採れているかな。

みんなで集めたプランクトンを顕微鏡で観察しました。動物プランクトンが動く様子は、大迫力です。

顕微鏡で見つけたプランクトンは、観察シートを使って種類を調べました。何種類見つけられたかな。
平成23年9月「シジミ漁業」
太田川で行われているシジミ漁業やシジミの生態などについて学習し、実際にシジミ漁業に使用される「じょれん」という道具にさわったり、シジミを使ったパスタを試食しました。
太田川でシジミ漁業を行っている広島市内水面漁業協同組合では、大粒のシジミを「太田川しじみ」と名付けてブランド化を進めており、広島市の「ザ・広島ブランド」にも認定されています。

太田川で行われているシジミ漁業やシジミの生態などについて学習しました。

シジミ漁業に使用する「じょれん」という道具に実際にさわってみました。とても重い道具で驚きました。

顕微鏡を使って、ヤマトシジミの幼生を観察しました。

大粒のシジミを使ったボンゴレ風のパスタを試食しました。手軽に作れるのでとても好評でした。
ボンゴレ風シジミ酒蒸しパスタ(2人分)
材料
- シジミ:200g (粒が大きい、太田川しじみが最適)
- スパゲッティ:200g
- 酒:100cc
- おろしにんにく:小さじ1/2
- 昆布茶:小さじ1
- 塩、しょうゆ、バター:適量
手順
- スパゲッティは塩を入れた熱湯でやや固めにゆでる。
- フライパンにバターとにんにくを入れて溶かし、シジミを入れて軽く混ぜ、お酒を入れてふたをする。
- シジミの口が開いたら、ゆであがったスパゲッティを加えて混ぜ、昆布茶を入れて味を調える。最後にしょうゆで香りづけをする。(小口切りした万能ねぎを散らしても良い。)
平成23年10月「海の珍味を食べよう」
今回の海辺の教室は、「海の珍味を食べよう」と題して、日頃あまり食べない海のいきものについて学習し、実際に試食してみました。
珍味というだけあって、見た目はちょっとグロテスクないきものもいましたが、それぞれ独特の味わいがあって皆で美味しくいただきました。

スプーンを使ってコイワシ(カタクチイワシ)のさばき方にチャレンジしました。スプーンで簡単にさばけるので、子どもたちには大人気でした。

調理前の珍味を観察しました。見慣れないものも多く、本当に食べられるか疑問に感じた参加者も多かったようです。

ちょっとグロテスクな珍味もありましたが、美味しく食べられるように工夫して調理しました。参加者は大満足。

コイワシの唐揚げ
広島ではおなじみの食べ方です。コイワシをこれだけたくさん食べるのは、他の地域からすると結構珍しいことなんですよ。

カメノテの味噌汁
カメの手に似ているのでカメノテと呼ばれます。磯などの岩の間に固まって生息しています。

ツブ貝の塩ゆで
ツブ貝は小さな巻貝の総称です。塩ゆでしたものを取り出して佃煮にしても美味しく食べられます。

ムラサキイガイのバター蒸し
セトガイやカラスガイとも呼ばれ、岸壁などでたくさん見られます。大きいものが手に入れば立派な食材になりますよ。

寒天ゼリー
和菓子などに使用される寒天は、実はテングサなどの海藻から抽出して作られています。今回は、テングサから抽出した寒天でミカンゼリーを作りました。
平成23年12月「カキ養殖」
今回は、広島の水産業を代表するカキ養殖について学習し、カキをむき身にする「カキ打ち」に挑戦しました。教室の最後には、美味しいカキ料理の試食もありました。

カキ養殖の歴史やカキの生態について学習しました。いかだで養殖されるようになるまでは、竹の枝に付いたカキを養殖していたりしたんですよ。

次はカキ打ちに挑戦です。カキのような二枚貝は、貝柱で殻を開閉しているので、貝柱を上手に切るのがカキを上手にむくコツなんですよ。

みなさん悪戦苦闘しながらカキ打ちをしました。広島では、カキを打つ人を「打ち娘」といいますが、打ち娘さんは1日に約3,000個もカキを打つんですよ。

最後にカキのバターしょうゆ焼きを試食してもらいました。カキは栄養が豊富で、これから旬を迎えるので、色々な料理に挑戦してたくさんカキを食べてくださいね。
カキのバターしょうゆ焼き(4人分)
材料
- カキ(むき身):400g
- バター:大さじ3
- しょうゆ:大さじ2
- こしょう:適量
- 酒:大さじ1
- レモン:1/2個
手順
- カキをざるにとり、ざるをくるくる回してぬめりを取る。
- フライパンにバターを熱し、カキを入れて強火で炒め、酒をふり、しょうゆとこしょうで調味する。
- 器に盛り、お好みでレモンを添える。
平成24年1月「カキ養殖」
先月に引き続き、カキ養殖をテーマに海辺の教室を開催しました。寒い屋外でカキ打ちを体験した後は、カキの簡単レシピ「カキの和風スープ」を試食してもらいました。

まずは、スライドやビデオを見てもらいながらカキ養殖について学習しました。

カキの打ち方について説明しました。形が不揃いなカキを上手にむくには、貝柱の場所をイメージすることが大事なんですよ。

説明を聞いた後は、さっそくカキ打ち体験開始です。いつも食べているカキは、このようにして打ち娘さんが一粒ずつ手でむいているんですね。とても大変な作業です。

カキ打ちの後は、カキの簡単レシピ「カキの和風スープ」を紹介し、カキ打ちで冷えた体を温めてもらいました。
カキの和風スープ(4人分)
材料
- カキ(むき身):200g
- 白菜:4枚
- だし汁:800cc
- 塩:小さじ1/2
- しょうゆ:小さじ2
- 水溶き片栗粉:適量
- ネギ:適量
手順
- カキをざるにとり、ざるをくるくる回してぬめりを取る。
- だし汁に白菜を入れ、火が通ったらカキを入れてひと煮立ちさせる。
- しょうゆと塩で味を調え、水溶き片栗粉でとろみをつける。
- 器に盛り、お好みでネギをちらす。
平成24年2月「魚の年齢」
魚の年齢魚調査をテーマに海辺の教室を開催しました。魚の鱗(うろこ)や耳石(じせき)と呼ばれる骨の一部には、木の年輪のようなものが刻まれており、これを調べることによって年齢を知ることができるんですよ。今回はメバルとシログチの年齢を調査しました。

スライドを使って、魚の体や年齢の調べ方について講義を行いました。

年齢調査に使ったメバルです。広島湾を代表する魚で、煮付けにするととても美味しい魚です。

今回は、シログチという魚の年齢も調査しました。別名をイシモチといい、体の大きさに比べて大きな耳石(じせき)を持っています。

まずは、生の状態で鱗(うろこ)を採取しました。食べるときは邪魔になる鱗(うろこ)ですが、今回は年齢を調べる大切な手がかりなので、丁寧に採取しました。

次は、耳石(じせき)を採取します。耳石は、目の後ろにあるので、今回は頭だけを煮付けにしました。

魚の頭を食べながら、耳石(じせき)を探しました。写真の大きい耳石(上)がシログチ、小さい耳石(下)がメバルです。

鱗(うろこ)や耳石(じせき)は、ルーペや顕微鏡を使って観察しました。今回のメバルは2歳から4歳、シログチは2歳から3歳でした。
平成24年3月「魚のおろし方」
今回の海辺の教室は、「魚のおろし方」をテーマに開催し、アジとコイワシ(カタクチイワシ)の三枚おろしに挑戦しました。ほとんどの参加者が、三枚おろしに挑戦するのは初めてでしたが、思い切りよく上手におろせていました。最後は、三枚におろしたアジを使ったアジのなめろうと骨せんべいを試食しました。

三枚おろしに使ったマアジです。手軽に手に入り、家でおろし方の練習をするにはぴったりな魚です。

広島ではお馴染みのコイワシも三枚おろしに挑戦しました。

今回は、講義は短めで、すぐに体験に移りました。まずは、講師による三枚おろしの実演です。

包丁を握ってアジをおろしていきます。まずは、包丁の先を使ってウロコを落としていきます。

頭と内臓を取り除いたら、思い切りよく、三枚におろします。骨に付く身の方が多い人もいたけど、初めてにしては上出来でした。

次は、スプーンと荷造りテープを使ってコイワシを三枚におろします。

頭の方からスプーンなどを滑らすように身をすくうと、きれいに三枚におろすことができます。家でもやってみたいという参加者が多かったです。

おろし方の練習で身がくずれた魚も、無駄なく食べられる骨せんべいとアジのなめろうを紹介し、試食しました。
アジのなめろう(4人分)
材料
- アジ:2尾(20cm程度のもの)
- 刻みネギ:適量
- 味噌:大さじ2
- おろし生姜:小さじ1/2
手順
- アジを三枚におろし、小骨と皮を取り除き、細かく刻んでおく。
- アジに味噌とおろし生姜を加えて、包丁で全体を混ぜながら粘りが出るまでたたいていく。
- 最後に刻みネギを混ぜ合わせて、器に盛る。