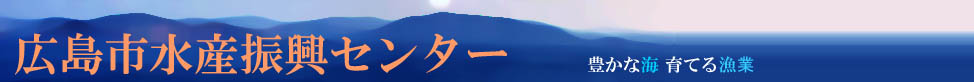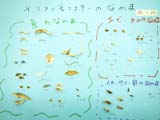今回は、水産振興センターで行っている水産動植物の種苗生産や稚魚の放流効果などについて学習しました。体験では、スズキの親魚へのエサやりや稚魚の見学を行い、最後にマコガレイの稚魚を放流しました。
平成24年度海辺の教室開催の様子
平成24年4月「育てる漁業:マコガレイ」

スズキの親魚へのエサやりに挑戦しました。水面で水しぶきをあげながらエサを食べる姿に参加者たちは大興奮でした。

次にオニオコゼを見学しました。背びれのとげに毒がありますが、とても美味しい魚です。当センターの放流で獲れる量が増えてきています。

ちょっと寄り道して、タッチングプール用のナマコやウニなどに触れてみました。ナマコの何ともいえない手ざわりが一番人気でした。

最後に、1月に当センターでふ化して育ててきたマコガレイの赤ちゃん(大きさ約3cm)を放流しました。元気に育ってくれるといいですね。
平成24年5月海辺のいきもの
今回の海辺の教室は、水産振興センターの前にある八幡川河口の干潟で生物採集などを行い、潮の満ち引きや干潟の役割について学習しました。普段接することが少ない干潟に、たくさんの生物が生息していることが分かり参加者の皆さんは驚いていました。網とバケツを持って、一度干潟に降りて遊んでみるのもいいですね。

干潟の役割などについて学習したあと、さっそく八幡川河口の干潟で生物採集を行いました。

上手に採集するポイントは、ブロックや海藻の回りを網でガサガサすることです。みなさんしっかりポイントを押さえていました。

短時間でしたが、こんなにたくさんの生物が採れました。この後、獲れた生物の名前を調べました。

トサカギンポ
護岸や岩礁でよくみられる。頭の部分にしま模様があり愛嬌のある表情をしている。

ヒモハゼ
砂泥域に生息するハゼの仲間。細長い体の形が名前の由来。

テッポエウビ
砂泥域に穴を掘って生息するエビの仲間。大きなハサミを使って「パチン」という音を出す。

ホシムシの仲間
砂の中穴を掘って生息する。口の部分に触手があり、これが星のように見えるのが名前の由来。

ヒラムシ
岩の隙間などに生息する。平べったい体で二枚貝に入り込み、中身を食べてしまうこともある。
平成24年6月メダカの育て方
今回の海辺の教室は、身近なメダカを使って卵の観察や顕微鏡の使い方などを学習しました。誰でも一度は見たことがあるメダカですが、実は野生のメダカはとても少なく、絶滅の危険があるとされています。メダカが自然に住めるような環境を残していきたいですね。

メダカの産卵や卵の特徴について学習しました。メダカは春から秋にかけて長い間卵を産みます。家でも簡単に飼えるので、飼育してみると面白いですよ。

次は顕微鏡を使って実際に卵を観察しました。顕微鏡を使うと肉眼では見えない小さな卵がどんな様子なのかがよく分かります。

卵を顕微鏡でのぞいた写真です。心臓の動きや血液の流れが観察できました。また、卵が水草などに付着できる仕組についても観察できました。

親メダカを使って、オスとメスの見分け方を紹介しました。尻ビレが大きいのがオスで小さいのがメスです。横から観察するとよく分かりますね。
平成24年7月プランクトン
今回の海辺の教室は、水中のいきものたちを支えるプランクトンについて学習しました。プランクトンは、自分ではほとんど泳がずに水の中を漂っているいきものを指し、その種類はとても豊富です。水の中で生活する魚や貝、大きなものではクジラまでがこのプランクトンをエサにしていて、食物連鎖を支えています。
今回は、ネットを使って自分たちでプランクトンを集めて顕微鏡で観察しました。小さないきものですが、海の中ではとても重要な役割を果たしていることを学びました。

水産振興センター前の港で専用のネットを使ってプランクトンを集めました。

集めたプランクトンを顕微鏡で観察しました。拡大して見ると、水の中を素早く泳ぐ動物プランクトンや色々な形をした植物プランクトンがたくさん観察できました。

キートセロスと呼ばれる、植物プランクトンです。カキやアサリなどのエサになります。大きさは約0.3mmです。

オニオコゼの稚魚を見学しました。水産振興センターで育てている稚魚にとってもプランクトンはとても重要で、ワムシと呼ばれる動物プランクトンを人工的に増やして与えています。
平成24年8月シジミ漁業
広島市内を流れる太田川に生息するヤマトシジミの生態やシジミ漁業について学習しました。
今回は、水産振興センターで試験的に育てているシジミの赤ちゃんの見学や恒例の冷凍シジミと生シジミを使った味噌汁の味比べ、そして、太田川の砂から実際にシジミの赤ちゃんを探す体験などを行いました。
シジミの赤ちゃん誕生から漁師さんが獲ったシジミを食べるところまで、とても盛りだくさんの内容で、参加者の皆さんは太田川しじみの大ファンになったと思います。

講義の後は、シジミの赤ちゃんを育てているところを見学しました。0.3mm程度の大きさですが、顕微鏡で観察すると立派にシジミの形をしていました。

シジミ漁業を行うためのジョレンという道具を実際にさわってみました。こんなに大きくて重い道具を使うなんて、シジミ漁業って大変ですね。

冷凍と生のシジミを使った味噌汁の味比べをしました。シジミは冷凍するとうま味が増すんですよ。冷凍しておけば保存にも便利で一石二鳥。

味噌汁ときたら、ご飯も欲しくなりますよね。今回は、大粒の太田川しじみを使った炊き込みごはんのレシピを紹介し、試食してもらいました。

最後は、川の砂利に混じったシジミの赤ちゃんを探す体験をしました。大きさ数ミリで、砂粒のような小さなシジミを探すのは一苦労。でも、宝探しみたいで、皆さん夢中になっていました。

今回紹介した大粒の太田川しじみを使った「シジミの炊き込みごはん」です。シジミのエキスがご飯につまっていて、味も栄養も抜群です。
シジミの炊き込みごはん(4人分:2合分)
材料
- シジミ:250g(粒が大きい太田川しじみが最適)
- 米:2号
- 水:1リットル
- ★しょうゆ:大さじ2
- ★酒:大さじ1
- ★みりん:大さじ1
- 野菜:ニンジン、マイタケ等適量
- 油あげ:適量
手順
- 1リットルの熱湯にシジミを入れ、貝殻が開くまで中火にかける。煮汁はボウルに取り(米の炊き汁で使用)、貝からシジミを取り出す。
- ★の調味料にシジミを1時間程度浸けて、シジミに味をしみ込ませる。
- 炊飯器に米を入れ、2のシジミと調味料を入れる。1の煮汁を2合の水量まで入れた後、好みの野菜と油あげを入れて、炊く。
平成24年9月海の珍味を食べよう
今回は、「海の珍味を食べよう」と題して、普段あまり食べることのない海のいきものの観察や試食を行いました。
色々な形の巻貝や亀の手に似た「カメノテ」、他にも海のいきものの中には食べることができるものがたくさんいます。見た目はグロテスクですが、それぞれ独特のうま味があって、みんな珍味のとりこになったようでした。

まずは、写真などで普段は食べないけど、実は食べられる海のいきものを紹介しました。

あらかじめ採集した「海の珍味」をタッチングプール形式で観察しました。巻貝、スジエビモドキ、ヒライソガニ、ムラサキイガイなど、たくさんの珍味を準備しました。

準備した珍味の一つカメノテを味噌汁にして試食してもらいました。カメノテは磯や護岸のすき間に生息していて、プランクトンを食べています。味噌汁などに入れるととてもいい出汁が出るんですよ。

水産振興センター前の港でツブと呼ばれる色々な種類の巻貝を観察し、塩ゆでにして試食しました。同じように巻貝にもたくさんの種類がいて、それぞれ違った味がするんですよ。
平成24年10月魚のからだ
今回の海辺の教室は、普段食べている魚のからだの仕組について学習する「魚のからだ」を開催しました。
講義では、魚の特徴や各部位の役割などについて学習しました。実習では、アジとアユを使って、口やヒレの構造、内臓の機能などについて魚をさわりながら学習しました。
実習に使った魚は、塩焼きにして皆で美味しくいただきました。

講義終了後、まずはアジの体を観察しました。口を開けるとエラとつながっているのがよく分かりました。

次は、魚の内臓を観察し、それぞれの役割を説明しました。エラを引っ張ると全ての内臓がつながっていることがよく分かりました。

アジのウロコやエラ、そして、水産振興センターで育てているアユの卵を顕微鏡で観察しました。授精して6日目のアユの卵では、心臓が動いていてみんな感動しました。

最後は、実習に使ったアジとアユを炭火で焼いて美味しくいただきました。魚ってやっぱり美味しいですよね。
平成24年12月カキ養殖
今回の海辺の教室は、広島の水産業を代表する「カキ養殖」をテーマに開催しました。
カキの生態や養殖の歴史、養殖方法などを学習した後は、カキを殻からはずしてむき身にする「カキ打ち」を体験しました。これからの季節、カキはますます美味しくなりますので、みなさん栄養満点のカキをたくさん食べてくださいね。

カキの生態や養殖の歴史などについて学習しました。太田川から運ばれてくる栄養やたくさんの島に囲まれた広島湾の地形が、カキ養殖に適しているんですよ。

次は、「カキ打ち」に挑戦です。写真の道具は、「カキ打ち」と呼ばれるもので、二本の刃を使ってカキをむき身にすることができます。
※一本刃のカキ打ちもあります。

色々な形をしていて、一見すると上下裏表が分かりずらいカキですが、上手にカキ打ちするコツは、貝柱の位置をしっかりイメージすることなんですよ。

みんな悪戦苦闘しながらも、最後はかなりの上達ぶりでした。プロの打ち娘さんたちは1日で3,000個以上のカキをむき身にするんですよ。カキ打ちについてはこちらをご覧ください。
平成25年1月チリメンモンスター
今回は、海辺の教室で大人気の「チリメンモンスター(略して「チリモン」)」をテーマに開催しました。
広島湾でも行われているシラス漁やチリメンジャコの製造工程などについて学習した後、チリモン探しや観察を行いました。見つけたチリモンは、種類を調べて、画用紙に張り付けたり、しおりや寒天ゼリーにして記念に持ち帰りました。海の中には、たくさんの種類のいきものがいて、お互いを支え合っているんですね。チリモンを通して、海のいきものの大切さがよく分かりました。

チリモンは、イワシ類のチリメンジャコに混じっている他の生物のことです。普段は、選別されて商品に混じることは少ないんですよ。

珍しいチリモンを見つけると嬉しいのは大人も子供も同じです。参加したお父さんも子どもに負けないぐらい一生懸命探していました。

見つけたチリモンを画用紙に並べてしおりを作りました。種類を書いたり、絵を描いたり、みんな色々なしおりを作っていました。

ちょっと珍しいとっておきのチリモンは、小さなびんに入れて寒天ゼリーにしました。海の中を漂っているようできれいですね。
平成25年2月魚の年齢
今回は、ウロコや耳石から年齢を調べる「魚の年齢」をテーマに開催しました。
魚のからだの特徴や耳石などから年齢を調べる方法を学習した後、メバルとシログチのからだをじっくり観察しました。耳石探しでは、煮付けにした魚を試食しながら慎重に魚の頭から耳石を取り出して、年齢を調べたところ、メバルは4歳、シログチは2歳半ぐらいでした。
耳石は、種類によって大きさや形が異なり、魚を食べながら宝探しをするような楽しみがあります。皆さんも家で魚を食べるときは是非挑戦してみてください。

今回はメバル(上)とシログチ(下)を使用しました。メバルは約18cm、シログチは約25cmでした。

年齢を調べる魚のからだを観察しました。ヒレやエラ、側線など魚の特徴について説明しました。

休憩中に耳石を取り出しやすいようにメバルを煮付けにしました。広島湾で豊富に獲れるメバルは煮付けに最適です。

まずは煮付けを試食して、続いて頭部から慎重に耳石を取り出しました。シログチはすぐに見つかりましたが、メバルは小さいので少し苦労しました。

左がメバル、右がシログチの耳石です。ご覧のように、シログチは耳石がとても大きく、これがイシモチという別名のゆえんです。
平成25年3月魚のおろし方
今回の海辺の教室は、丸ごとの魚を三枚におろす「魚のおろし方」をテーマに開催しました。
包丁の扱い方や手順を説明して、アジの三枚おろしに挑戦しました。パック入りの切り身や刺身は手軽に食べられてとても便利ですが、丸ごとの魚をおろすことで、内臓や骨がどのようになっているかが分かり、魚を美味しく、上手に食べられるようになります。
上達するコツは、思い切って包丁を動かしていくことです。お子様だけでなく、大人も一緒になってご自宅で挑戦してみてください。

まずは簡単に包丁の扱い方や魚をおろす手順を説明しました。基本的なおろし方はほとんどの魚で同じ手順でできるんですよ。

今回は、手頃で美味しく食べられるアジの三枚おろしに挑戦しました。最初は恐る恐るでしたが、全員が三枚おろしに成功しました。

コイワシはスプーンや荷造り用テープで簡単に三枚おろしができます。小さなお子様にもできる三枚おろしです。

アジのかば焼きと骨せんべい、コイワシの唐揚げを試食してもらいました。自分でおろした魚で色々な料理に挑戦してみてください。
アジの蒲焼き(2人分)
材料
- アジ:3尾
- 片栗粉:適量
- 水:1リットル
- ★しょうゆ:大さじ1
- ★砂糖:大さじ1
- ★酒:大さじ1
- ★みりん:大さじ1
- ★水:大さじ2
- 油:適量
手順
- アジを三枚におろし、キッチンペーパー等で水けを切った後、片栗粉をまんべんなくつける。
- フライパンで焼き、火が通ったら一度皿にとる。
- ★をフライパンに入れ、煮立ったら再びアジを入れタレをからめる。